ESSAY
運命の相手とは?

先日、久しぶりに東京の友人と出会う機会があった。約1年ぶりの再会という事もあり、仕事や趣味の話などで大いに盛り上がった。そして、話の途中で、”運命の相手”について話し合う事があった。ここでいう運命の相手とは、恋人・友人問わず、自分が生涯を通じて関わっていきたいと思うような人物の事である。友人曰く、運命の相手は、確率と密接に結びついているのではないか、とのことだった。それは、特定の人物と出会う可能性が低ければ低い場所ほど、その場所で出会った相手があたかも運命的に引き合わせられたかのごとく感じられるのではないか、という意見である。これについて、もう少し具体的を交え話をしてくれた。
彼の考えでは、運命はそもそも人と出会う確率と結びつきがある。例えば、同じ面積を持つ人口100人の村Aと人口1万人の村Bを想定してみよう。人口1万人の村Bでは、母数が村Aに比べて多いので不特定の誰かと出会う可能性が高くなる。それに対し、人口100人の村では、母数が村Bに比べて少ないので、そもそも人に出会う可能性が村Bに比べて低くなる。最も単純に考えれば、村Aで単位時間あたりに誰かに出会う確率は、村Bのそれに比べておよそ1%程度しかない。その為、そもそもの出会いの可能性が少ない場所ほど、気の合う相手を見つけた時に運命のパートナーと見なす傾向が強まるのではないか、というのが彼の考えである。
確かにそもそも人に会う確率が低い場合に、理想の相手と出会うというさらに起こりにくい事象を運命と感じる、という考え方は頷ける。ただ、もし確率を人と出会う確率ではなく、コミュニティーに存在する特定の人物と出会う確率と考えたらどうだろうか。その場合、村Bの方が村Aより多くの人が住んでいる為、全ての人の中からある特定の1人を選べる確率はBの方がはるかに小さい。そうすると、人口の多いBのほうが、多くの可能性の中から起こりにくいわずかな可能性を選んだという意味で、より”運命の相手”に近づくのではないだろうか。この点を指摘すると、友人は「確かにその点については見落としていたね…」と頷いていた。確率を軸とした考えでは、何を起こりにくいと認識するかで運命の感じ方が変わるというのは非常に興味深い指摘であった。その一方、“運命”という人間の認識が介在してしまう問題に対しては、なかなかに定量的な議論は難しいと感じた。
続いて友人は、今度は私に「じゃあ反対に”運命の相手”ってなんだと思う?」と逆質問してきた。これに対し私は、自分の意思との関わりで”運命”というものを捉え答えを試みてみた。すなわち、「極力自分の意思決定を挟まないで出会った相手、乃至は、見えない力によって”必然的に出会えた”と感じられるパートナーこそ運命の相手と呼ぶのではないか」と。
”運命”という言葉の意味を考えると、運命の相手とは、本人の意図的な選択とは無関係に巡り合ったパートナーであるように思える。出会いが受動的であった場合において、その出会いはおそらく確率的なものとみなせるだろう。しかし、それが自分にとって理想的であった場合にはどうだろうか。あたかも、その出会いは神の見えざる力に決定づけられた必然、すなわち”運命”と感じてしまうのではないだろうか。しかし、ここで私はさらに思う。運命とは”誰かと出会いたい”という意思とは無関係に生じた出会いにだけ生じうるものだろうか。アプリやパーティーなど、現在では出会い自体を目的とした機会も多い。そうした機会で生じた出会いに、”奇跡的な必然”は存在しないのだろうか。そんなことはない。意図的に相手との出会いを求めた場合においても、相手が同じタイミングで同じ内容の行動を起こしていなければいけない。さらに、つながりを持ち続けたいというマインドを共有できなければならない。そうした偶然の重なりがなければ、その人と関わりを持ち、パートナーとなり得る事はなかったはずである。この偶然は、十分に”奇跡的な必然”と思い込むに足る事象ではないだろうか。そう考えると、運命の相手とは、本人が出会いを意図するしないにかかわらず、”なんらかの必然に導かれたと思える”ほど、心のつながりを持ちたい相手ということだろう。
人は1日の中で約35000回もの選択をしているとされている。その一つ一つが未来を決める重要な要素である。その中には、出会いに関わる選択も多分に含まれていることだろう。いつどこへ出かける、出先でちょっとした寄り道をする、そんなありふれた選択も誰かと出会うきっかけになる。その時その時の選択、そして結果としてもたらされる出会いひとつひとつの偶然を大事にしたい。それがきっと、その人だけの”運命の相手”に結びつくのだろう。

『論語』は中国より日本にもたらされた最も古い書物であると言われ、それは『古事記』の時代にまでさかのぼることができる。儒学は足利時代、宋の朱熹による古典学改革を経て、江戸時代徳川家康によって国教的な地位を与えられた。「論語」が幕府によって武家社会を支える正式な学問として公認された理由は大きく分けて3つあると考えた。
1つは、戦国の乱世が平定され階級社会が確立によるものである。ようやく手にした平安の世において、人間社会の秩序を尊重する朱子学が為政者にとって都合のよい学問であったからである。
2つ目は神秘主義に陥らず、文章が日常の具体的事柄を取り上げながら書かれていて非常に読みやすかったこと。
3つ目は人間としてもっとも重要な愛(仁)を増大させることが為政者の役割と述べ、その強い理想主義が深く人々の心に訴える力を持っていたことがあげられる。
孔子の目指す政治の形は「徳治主義」である。政治家は政治と教育により「仁」の支配する社会を実現する必要がある。学問を修め「仁」と「礼」を体得した理想の人物を”君子”と呼ぶ。君子となった君主が徳をもって政治にあたり、礼によって整え治めていけば、人民は恥を知り慎んで自分をただすようになるという〈修身、斉家、治国、平天下〉。孔子は文化国家である周王朝の再現を夢を見ていた。周公は礼と楽という文化法則を定めた偉人である。周王朝は数百年前になくなってしまったが、自分こそその後継者であり、それが自らもって生まれた天命であるという強い自負心を持っていた(孔子50にして天命を知る)。孔子は思想の中心に常に「政治」を置き、理想的な社会の実現を自ら引き受けようという理想に燃えていたのである。
孔子はまた、下剋上と殺戮の世の中に生きても人間の可能性対して強い自信と信頼を置いていた〈徳不弧、必有隣〉。人間の本性は近接したものであり、先天的な善人と悪人はいない〈性相近也、習相遠也〉。もともと人間の間に区別はなく教育によって分かれるのだ〈有教無類〉。教育の力を信じ、若者に希望を託したその姿は〈後世可畏〉、街に出て魂をいたわることの大切さを説き続けたソクラテスに、評判芳しくない国王の誘いに心を揺り動かされ、王の後見として政治の力を信じ、仁に満ちた理想国家を実現しようとした点は、プラトンの姿を彷彿させる。
さらに孔子は、立派な人間になるためにはたゆまぬ努力が必要であると説く〈人能弘道、非道弘人〉。人は己の努力によって完成されるのである。しかし、どんな努力を積み重ねても社会に認められる確証はない。それでも決してあきらめないこと。「仲弓」を例にとり、努力は必ず人から認められると希望を語る。そして孔子は、人間の可能性を説きながらも、その限界をも自覚していた。人間の力ではどうすることもできない運命的な事柄を「命」と呼び、50にして「天」から与えられた「使命」を自覚した孔子は強い政治改革の志を示した。私たちの運命は天の意志に決められているかもしれない。だが、そうした天によって制約をかけられた世界でも、人は生き抜き、人間の可能性を説く孔子の姿にはまさに感動を覚える。また、孔子は行為について「中庸」を知って分を守ることを主張する。人間に課された限界を知ったうえで人間の希望に向かって進むべきことを穏やかに説いている。人間は愛情の動物であり、その拡充が人間の使命であるとするなら、過去の人間の経験を学んで、社会の法則を知らなければならない。孔子が「学問」を最も尊んだゆえんであろう。
以上、吉川幸次郎氏の『「論語」の話』を参考にその魅力を語ってみたが、孔子の思想の根源に論理を超えた純粋な人間的感情の発露を知り驚きを覚えた。論語に興味のある方は、是非一度手にとっていただきたいと思う。

先月の10月、Amazonプライムでバチェロレッテという番組が放送された。バチェロレッテとは、番組のヒロインとなる一人の女性が、複数の男性たちの中から、将来パートナーとなる男性を見つける番組だ。バチェロレッテでは、そんな未来のパートナーを見つける為、様々なイベントや企画を通じ、お互いをよりよく知っていく為の機会が設けられている。そんな恋愛リアリティ番組という事もあり、ストーリーの中ではしばしば「愛とは何か?」というテーマが取り上げられている。
このテーマに対し、ある参加者は「愛とは生きる行為そのものであり、私たちの日常生活全てに愛が詰まっている」と考えたり、ある者は、「自分を犠牲にしてでも守りたいと思う気持ちこそが愛である」という考えを示している。
「愛」とは、人を思う気持ちの一形態ではあるのだろう。しかし、その具体的な解釈については、人の価値観はそれぞれ異なり、多様な理解の仕方がある。では、「恋愛」についてははどうだろうか。恋愛も多分に主観的な要素を含む。というより、自分の感情が先行する分、愛よりさらに主観的なイメージが有る。恋心を抱くきっかけは人それぞれであるものの、他者が自分が好きになった相手に対して同じように恋心を抱くとは限らない。逆もしかりである。しかし、”恋愛”自体は多くのヒトが共通して経験する。では、”恋愛”はそもそもどのように成り立っているのだろうか。恋愛の成立について、思想家の内田樹氏はこのように述べている。
恋愛というのは、「はたはいろいろ言うけれど、私にはこの人がとても素敵に見える」という客観的判断の断固たる無視の上にしか成立しないものです。自分の愛する人が世界最高に見えてしまうという「誤解」の自由と、審美的基準の多様性(というより「でたらめさ」ですね)によって、わが人類はとりあえず今日まで命脈を保ってきたわけです。生物種というのは、多様性を失うと滅亡してしまうんですからね。
(中略)
私たちが自分自身の恋愛関係の中で経験している愉悦や幻滅や快楽や絶望は、まわりにいる人間には決して同一のリアリティをもって経験されることがありません。でも、それこそが恋愛という経験のいちばんすばらしいところではないでしょうか?だからこそ、みなさんも「世界最高の恋人」にいつか出会えるのではないかという願いをひそかに胸にして、毎日暮らしていけるわけです。
(中略)
「どきどき感」のこれはひとつの典型なんですけれど、「誰も気づいていないことに、私だけが気づいていた」という経験て、たぶん人間にとって、「私が私であること」のたしかな存在証明を獲得したような気になるからでしょうね。恋も科学の実験もそういう意味では、とても人間的な営みなんです。恋に落ちたときのきっかけを、たいていの人は「他の誰も知らないこの人のすばらしいところを私だけは知っている」という文型で語ります。みんなが知っている「よいところ」を私も同じように知っているというだけでは、恋は始まりません。
– 内田樹『先生はえらい』-
相手の笑った顔や何気ない気遣い…そういった仕草でも、誰もが全く同じように感じ取っているわけではない。「私だけが気づいている魅力」と、「あなたが気づいてくれた私だけの魅力」を発見するときにこそ、人は相手と自分の存在価値を強い主観の元に認めて、その関係性を本物の「恋」として実らせるのだろう。多様性はヒトという生物種の特徴であり、我々のアイデンティティの源であるが、恋愛にはその典型を見ることができる。バチェロレッテ参加者の皆様には、是非今後も”わがまま“に「私たちしか知らないお互いの魅力」を共有できるパートナーを見つけてほしいものである。
参考文献
内田樹(2005) 『先生はえらい』 筑摩書房

最近、漢字にはまっている。普段、プログラマーという職種でコードばかり入力している事もあり、活字を書くのが最近とても楽しく感じているのだ。そんな楽しみを分かち合いたいと思い、友人にその話をした所、「おお、それはいいね!」と私事のように喜んでくれたのだが、それと同時に「でもどうして漢字なの、活字を書きたいならもっと将来使いそうな文字や言葉を書き取ったりした方がいいんじゃない」との返事をもらった。
友人の指摘は尤もかも知れない。何せ、私が今学んでいる漢字は既に常用漢字として使われておらず、おそらく今後使う機会が滅多にないといっていいほどマイナーな漢字ばかりだからだ。活字に飢えているのなら、おそらく英語や中国語を書き取ったり、資格試験の用語を覚えた方が遥に実用的だろう。
だが、この一見”無駄”のように思える学びを、私は”実用的”な学びに対して価値が薄いものかと問われれば、否と考える。そして、もしその理由を尋ねられたなら「いつか役に立つかもしれないから」と答えるだろう。しかし、「そんな曖昧な返事は答えになっていない」と言う人がいるかも知れない。それに対し、私はこの「根拠なき根拠」とでもいうべき理由を再考するとき、「ブリコラージュ」という言葉が頭に浮かぶ。
ブリコラージュとは、人類学者のレヴィ=ストロースが提唱した用語である。レヴィ=ストロースは、南米のマト・グロッソの先住民達を研究し、彼らがジャングルの中を歩いていて何かを見つけると、その時点では何の役に立つかわからないけれども、「これはいつか何かの役に立つかも知れない」と考えて袋に入れて残しておく、という習慣があることを発見した。そして、実際に拾った「よくわからないもの」が、後でコミュニティの危機を救うことになっていたのである。
こうした事例は何も先の例に限った話ではない。例えば、アメリカにおけるアポロ計画は、少し引いて考えれば、それがこの先何の役に立つのかわからないプロジェクトである。しかし、アポロ計画によって医療の分野(特にICU(集中治療室))に大きな貢献がもたらされた。それは、宇宙飛行士の生命や身体の状況を、遠隔地からモニターして、何か重大な変化が起これば即座に対応するという、アポロ計画のような長期の宇宙飛行においての必要性から生じた技術が誕生したからである。
また、1979年に発売された「ウォークマン」は、当時SONYの名誉会長だった井深大が「海外出張の際、機内で音楽を聴くための小型・高品質のカセットプレイヤーが欲しい」と言い出した事を契機に開発された特注品であった。この商品を同じく創業経営者の盛田昭夫に見せたところ、盛田もこれを大いに気に入り、製品化にゴーサインが出されることになった。だが、 現場の者はこの指示に反発した。それは、当時の市場調査から、顧客が求めているのは大きなスピーカーであり、多くの人がラジオ番組を録音して楽しむためにカセットプレイヤーを購入していることを知っていたからである。しかし、現場の予想とは相反し、ウォークマンは世界で累計販売台数4億台以上に上る大ヒットを遂げたのである。
その他にも、1935年にアメリカのデュポン社によって発明された世界初の合成繊維であるナイロンは、デュポン社が企業内に基礎研究の場を設けた事がその成果へと繋がり、軍事技術の開発の為に作られたインターネットは、今ではソーシャルネットワークやIoTといった社会インフラの基盤を担っている。
勿論、その学びの用途がはっきりしている目標設定、例えば、受験勉強であったり資格試験といったものは、目的に裏打ちされた強い動機を与えるため、あるに越した事はない(というよりむしろあった方がいい)。ただ、前述の事例を見返せば、思いもよらない方向で達成される大きな発見や成果の裏には、直感や好奇心に導かれて行う学びや行動があった。こうした学びや行動は、既存の枠組みにとらわれない見方・展開の発想を醸成するには必須であるとも言えるだろう。そうすると、今は一見”無駄”に見えるかもしれない漢字の書き取りも、いつか思いもよらない形で何かと有機的に結びつき、自分や社会に還元できる日が来るのかもしれない。人間が進化させてきた”学び”の本質は、純粋な好奇心に動機を得たものにこそ秘められているのではないだろうか、と改めて考える今日このごろである。
引用文献
山口周(2018) 『武器になる哲学』 KADOKAWA
山口周(2017) 『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』 光文社

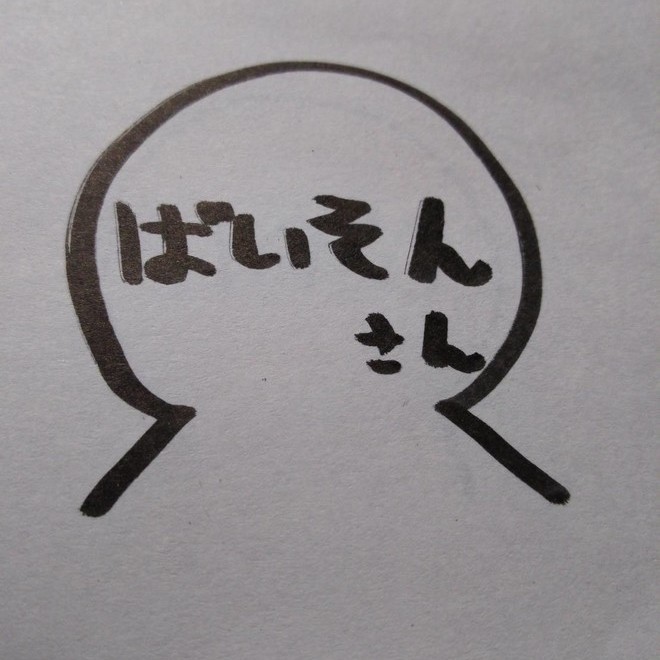
去年の10月から交換日記を始めた。
しかしその相手は知人でもオンライン上で知り合った方でもない。
友人の子供だ。
そのきっかけは、自身がフリーランスとして働いていた頃、仕事をしながら友人のお子さん(年中さんと小学2年生)の面倒を見る機会があった事だ。その折、自身がプログラマーという事もあり、ローマ字入力の方法を子供たちに教えてみた。しかし、ただ教えてもその学んだ知識を活用しなければ意味がない。そこで友人から「せっかく教えてもらった知識を使わないのはもったいないから、僕と子供と一緒にオンラインで交換日記を始めてみないか」と頼まれた。そんな経緯もあり、お子さんのご家族に混じって交換日記を始める事となった。その甲斐あってか、お子さんのローマ字の習得が思いのほか早く、半年で互いの日記の投稿数が200を超えるまでにもなった。そしてさらに、日を追う事にその文章量は増し、今では読書感想文を書いたり、日記を書くために漢字を自己学習するまでにもなっている。
そんな事情もあるせいか、子供の親御さんから「毎日息子が楽しそうに日記を書いている。きっかけをくれてありがとう」と言われるまでにもなった(恐縮です…)。そして私自身、この交換日記の体験を通じて、子供の”自発的な学習能力”について興味が湧き調べて見た。すると、どうやら近年の教育分野の世界では「非認知能力」という力が注目されているらしい。
「非認知能力」とは、簡単に言ってしまえばやり抜く力・好奇心・自制心といった数字で測る事のできない力や資質を指す。 それに対し「認知能力」とは、読み書きや学力といった数値(IQ)で測れる力や資質のことを指す。そして近年、長年にわたる子供の追跡研究調査の結果から、非認知能力が認知能力と同等、もしくはそれ以上に子供が将来社会で生きていく力として強い影響力を与えている事が明らかとなっている。
その代表的な事例としてあげられるのは、「ペリー就学前プロジェクト」だろう。これは、ノーベル経済学賞を受賞したジェームズ・J・ヘックマン教授が行った就学前教育の社会実験である。この実験では、経済的に恵まれない3歳から4歳のアフリカ系アメリカ人の子供たちを対象に、毎日平日の午前中は学校で教育を施し、週に一度午後に先生が家庭訪問をして指導にあたるというものだ。この就学前教育は2年間ほど続けられ、この実験の被験者となった子供たちと、被験者とならなかった同じような経済的境遇にある子供たちとの間で、その後の経済状況や生活の質にどのような違いが生じるかを約40年間にわたって追跡調査が行われた。その結果、10歳の時点では、就学前教育を受けたグループと受けなかったグループの間には、IQの差は観察されなかった。しかし、40歳になった時点で比較した所、就学前の教育の介入を受けたグループは比較対象グループと比べて、高校卒業率や持ち家率、平均所得が高く、また婚外子を持つ比率や生活保護受給率、逮捕者率が低いという結果が出たのである。
また、ポール・タフ著の『私たちは子供に何ができるか』では、子供の非認知能力を育む上で働きかけるべき大切な場所は、子供自身ではなく、環境であると紹介している。例えば、幼い時期に経験した高レベルのストレスは、前頭前皮質、つまり知的機能をつかさどる最も繊細で複雑な脳の部位の発達を阻害し、感情面や認知面での制御能力を妨げる。さらに、子供が感情面、精神面、認知面で発達するための極めて重要な環境は家であるとしている。これは、特に子供が動揺しているときに、親が激しい反応を示したり予測のつかない行動を取ったりすると、後々子供は強い感情をうまく処理することや、緊張度の高い状況に効果的に対応する事ができなくなるとされている。しかし、その反対に、子供が瞬間的なストレスに対処するのを助け、怯えたり癇癪を起こしたりした後に落ち着きを取り戻すのを手伝い事のできる親は、その後の子供のストレス対処能力に大いにプラスの影響を与える事が明らかとなっている。
こうした研究結果を踏まえると、今行っているオンライン交換日記も、私のアウトプットに対するお返しが、お子さんたちのさらなる学習意欲を促し、彼らの非認知能力を養うのに一役買っているのかもしれない。その一方、子育ては一つ違えば子供の考えやその後の人生を大きく左右してしまうため、その責任の大きさを感じて怖くもなってしまう。しかしいずれにしろ、子は私たち大人の姿、特に親の後ろ姿を見て育っていくのは事実であり、幼少期はその背中からあらゆるものを自分なりに受け取り学びとれる子供自身に与えられた好機 (チャンス) である。そう考えると、子供にはより多くの新しい世界に触れられる機会を与えてあげ、その体験から好奇心という芽を育ませ、その芽を摘み取らず水を注いでいく事こそが私たち大人ができる最良のプレゼントではないかと思っている。今行っている交換日記も、お子さんたちがこの経験を通して何か自分に還元できるものを見つけ出し、少しでも心豊かな人生を歩んでてもらえれば、私としてこれほど嬉しい事はない。そう思いながら、今日もどんな日記を書こうかと思案するのである。
参考文献
ジェームズ・J・ヘックマン(2015) 『幼児教育の経済学』 古草 秀子 訳 東洋経済新報社
ポール・タフ(2017) 『私たちは子どもに何ができるのか』 高山 真由美 訳 英治出版
あとがき
今回、幼少期の教育に焦点を当ててエッセイを書いてみましたが、教育経済学の観点から見た子育て理論も大変面白いものがありました。その一つとして、「ご褒美理論」という方法がありますが、これは、子供を勉強させる為にお金やものといったインセンティブを与え、子供に勉強を促すやり方だそうです。アメリカのある実験で、このご褒美の因果関係を明らかにした実験が行われましたが、その内容は、”学力のインプットとアウトプット、どちらが子供に対してより効果的であったか”という実験でした。
実験では、”テストでよい点を取った時のご褒美(アウトプット)”と”本を読んだ時のご褒美(インプット)”の組に分かれて検証が行われましたが、その結果、学力テストの点数が向上したのは、”本を読んだ組(インプット)”だったそうだ。その理由は、人には目先の利益や満足を優先してしまう傾向がある為、テストでよい点を取るご褒美は、インプットと比べると少し遠い未来の話となってしまうからだそうだです。また、テストでよい点を取るご褒美は、どうすれば点数が上がるかといった勉強の道筋が示されていない為、学力の向上まで結びつきにくかったそうです。それに比べインプットは、本を読み、宿題さえ終えればよいわけなので、子供たちにとっても何をすればよいか明確です。その為、本を読んだ時のご褒美はテストでよい点を取った時のご褒美よりも効果的だったそうです。
参考文献
中室牧子(2015) 『「学力」の経済学』 ディスカヴァー・トゥエンティワン


去年の10月、私は都内の民間講座で昆虫食マイスターという講義を5回にわたって受講した。この講座では、文字通り昆虫食について学んでいくのだが、その講義内容が実に面白い。例えば第1回の講座では、多摩川の土手に行ってバッタを捕まえて食したり、第2、3回目では、コオロギ・カブトムシといった昆虫の味見に加え、オーストラリア原産のマダガスカルゴキブリに触れることもできた。そして極め付けは、昆虫を使った調理実習だ。実習ではミルワームという幼虫を使ってパンクッキーを作ったり、イナゴから出汁をとりつけ麺を食べたりと、何ともインパクトが強烈な講義の数々であった。



そんな経緯もあり、昆虫食の話を興奮しながら周りに話したが、「よく昆虫なんて食べられるね….。」「昆虫食ってあれでしょう…確かゲテモノって言われる食べ物」「昆虫以外の食べ物がこの世から消えたら、その時はもう死ぬ時だよね」といった否定の数々であった(勿論、興味関心を示してくれた方も中にはいる)。確かに彼らの言うことに全く共感できない訳ではない。何せ、私自身も昆虫はどうみても動物と比べたら美味しそうには見えないし、唾を飲み込むほど食欲を掻き立てられるかと言われると、彼らと同じく首を傾げてしまうからだ。では、なぜ私は今回昆虫食の講義を受講しようと思ったのか…。それは、「昆虫食が好きだから!」という理由よりも、昆虫食という「食」に対して以前から非常に関心があった事がその理由としてあるからだろう。
現在、昆虫は世界で約20億人もの人々に食されているが、人類が昆虫を食べ始めた歴史は長い。その歴史を遡ると、アウストラロピテクスが400万年前に誕生して以来からとなるが、有史時代になると、昆虫食について書かれた文献が見られるようになる。例えば、哲学者・アリストテレスは『動物誌』にこう書いている。
地中で最大限に大きくなったセミの幼虫は若虫になる。その殻が壊れる前がいちばん美味しい…(成虫なら)まず雄で、交尾後がよく、ついで白い卵がいっぱいの雌が美味しい
詩人・アリストファネスは、バッタが鶏肉屋で「四枚の羽をもつ鶏肉」として売られていたと書いており、歴史家・ヘロドトスは乾燥イナゴについて次のように記している。
エジプトとフェゼンのあいだの住民はイナゴを追いかけ、それを天日で乾かし、粉にし、ミルクの上に振りかけるーこの滋養分のある飲み物は、現代の調製された乳製品に匹敵することは間違いない。
また、『コーラン』によれば、マホメットはバッタを食べながら「二つの死体(動物)と二つの生命ー肝臓と脾臓、魚とバッターを食べるのは法の許すところである」と説教しており、『聖書』では、昆虫食についてこのような記述がされている。
「ヨハネは、らくだの毛皮を着、腰に皮の帯を締め、いなごと野蜜を食べ物としていた」(「マタイによる福音書」三章四節)
羽があり、四本の足で動き、群れを成す昆虫はすべて汚らわしいものである。ただし羽があり、四本の足で動き、群れを成すもののうちで、地面を跳躍するのに適した後ろ肢を持つものは食べてよい。(「レビ記」十一章二十 – 二十二節)
このように、昆虫食は人類にとって昔から大変馴染み深い食べ物として食されているわけだが、現代においては、化学肥料の開発やグローバル化に伴う食文化の移り変わりもあり、昆虫を食す機会が徐々に失われているように見える。しかし近年、「世界のベストレストラン50」で1位を獲得した「NOMA」が、アリやコオロギを使ったメニューを提供して話題となり、篠原祐太さんが日本で世界初の「コオロギラーメン」を開発したりと大きな注目浴びている。そしてさらに、昆虫食を未来のスーパーフードとして期待する視線は特に熱い。
2013年、国連食糧農業機関(FAO)が人口増加や温暖化対策の一つとして”昆虫食”を提案したが、実際に昆虫食のサスティナビリティは驚くほど地球に優しく、生産効率に優れている。例えば、飼育変換効率について見てみると、肉を1キログラム増やす為には、牛は10キログラムの餌が必要だが、コオロギはたったの2キログラムで済む。また、可食部率では、牛が40%なのに対し、コオロギは脚と外骨格部分を除いた体重の80%を食べる事ができ、飼育スペースと生産量の観点からみても、1立方メートルあたりのカイコ幼虫の生産量が221キログラムなのに対し、ブロイラーが105キログラムと、省スペースでの大量生産が可能である。さらに、温室効果ガス排出量を家畜とで比較した結果では、ミールワームは豚の10分の1以上、牛の400分の1程度で、ヨーロッパイエコオロギでは豚の 50 分の1、牛の2000分の1程度に抑えられると報告されている(水野, 2016)。 このように、昆虫食は畜産動物と比べ生産性や環境面に大変優れており、しかも、人体に必要なエネルギーも十分に賄えるので、まさに昆虫食は文句の付けようがないスーパーフードといっていいだろう。(ちなみに、シロアリの栄養価は非常に高く、1食あたり23グラム(大さじ一杯半)で必要な栄養素を摂取できる)。
近年、地球資源の枯渇が著しくなる一方で、世界人口は増加の一途を辿り、2050年には100億人を突破すると予測されている。今はまだ、肉や魚といった動物性食品がスーパーに立ち並ぶが、今後数十年先の食糧事情を見越した時、その未来の行く末はどうなっているかわからない。近い将来、当たり前のようにスーパーに昆虫が立ち並び、スシネタも昆虫にとって変わる日が来るのかもしれない。

参考文献
内山昭一(2012) 『昆虫食入門』 平凡社
内山昭一(2019) 『昆虫は美味い!』 新潮社
水野 壮『現代の昆虫食の価値―ヨーロッパおよび日本を事例に―』(フェリス女学院大学国際交流学部紀要、2016)

昆虫食レストラン
・獣肉酒家 米とサーカス 渋谷パルコ店
・珍獣屋
豊かで強い国を目指す為、政府による市場への規制を撤廃し、競争を促進することで国の成長を高める経済戦略がある。その思想的背景としては、アダム・スミスの名が挙げられ、『国富論』はこのメッセージを補強するものとして援用される。しかし、自由放任主義者、急進的な規制緩和論者として語られるスミスのイメージについて、私は詳細な検討をしたことがない。そこで今回、堂目卓生氏の著書『アダム・スミス -「道徳感情論」と「国富論」の世界-』を起点に、人間本性の考察に立ち返り検討してみようと思う。

出典:Wikipedia
まず、私たちは、利害関係がなくとも常に他人に関心を持ち、他人の感情や行為に共感しようとするが、他人もまた、私たちに関心を持ち、その感情や行為に共感してくれることを望む。しかし、すべての人から共感を得ることは難しい。そこで私たちは、成長と経験を重ね、「胸中に公平な観察者」を形成する。この公平な観察者は、常に私たちに公平な判断を与えてくれる存在である。時に世間の評価は偶然によって影響を受け、公平な観察者の評価とは異なることがある。私たちの中の「賢明さ」は、公平な観察者の賞賛を求め、非難を避けようとする。しかし、私たちの中の「弱さ」は、胸中の観察者の評価よりも世間の評価を重視し、自己欺瞞によって、公平な観察者の非難を無視しようとする。
そこで、私たちの中の「賢明さ」は、胸中の観察者の賞賛を求めるように行動することを一般的諸規則として設定する。これが「義務」の感覚であり、正義に関しては、それを「法」として定式化する。法と義務の感覚によって、社会秩序は維持されるが、私たちの「弱さ」は、しばしば義務の感覚を弱め、私たちに法を犯させるため現実の社会秩序は完全なものにはならない。
私たちは、他人の歓喜に対しては喜んで共感するが、悲哀に対しては共感をためらう。歓喜への共感は私たちに快楽をもたらし、悲哀への共感は苦痛をもたらすからである。富や高い地位は私たちに歓喜をイメージさせ、貧困や低い地位は悲哀をイメージさせる。私たちの中の「弱さ」は、歓喜をイメージさせる富や高い地位を求め、悲哀をイメージさせる貧困や低い地位を避けようとする。本来最低水準の富さえあれば、それ以上の富の追加も私たちに幸福をもたらすものではない。しかし、私たちは富と地位の幻想にとらわれて「財産への道」を歩む。「財産への道」を進むことによって、社会全体の富は増大し、より多くの人間に生活必需品が分配される。一方、私たちの中の「賢明さ」は、徳と英知が真の幸福(心の平静)をもたらすことを知っており、「徳への道」をめざす。私たちは、「財産への道」を進む過程で徳と英知を身につけることができる。
ところがしばしば、「財産への道」は「徳への道」と矛盾することがある。このとき、「徳への道」を優先させ、フェア・プレーのルールに従えば、社会の秩序は維持され、社会は繁栄する。私たちがあくまでも「財産への道」を優先させ、フェア・プレーのルールを侵犯する時、社会の秩序は乱れる。社会の秩序と繁栄をもたらすものは、「徳への道」の追求と矛盾しない「財産への道」の追求、言い換えれば正義の感覚によって制御された野心と競争だけである。
上記展開を踏まえたうえで、以下いくつかの議論を展開したい。
第一に「市場」の成立に対するスミスの視点は非常に斬新なものである。市場は本来互恵の場であって競争の場ではないとスミスは主張する。虚偽・結託・強奪は市場から退去しなければならない。社会をなして生活する人間は常に他者からの共感を求める。「説得性向」と呼ばれるこの心理は、日常私たちが常に他人と言葉を交わす場面に見られる。相手に自分の感情、意思、意見を伝え相手の共感を得ようとする。他者が共感してくれれば喜び、共感を得られなければ失望する。私たちは他者からの共感を得るために、一生懸命言葉を伝える。説得性向は、他者からの共感を得ることを目的に、他者と言葉を交換しようとする人間の本性的性向なのである。
この説得性向に基づいて言葉を交換する関係ができれば、それを物との交換に展開することは容易い。私は、説得して自分の提案に共感してもらったうえで、相手の物を手に入れる。相手もまた同様である。両者が相手の提案に共感した時、はじめてそこに物の交換が成立する。「人はだれでも、生まれてから死ぬまで、生存のために他人からの世話を必要とする」「これらがすべて、愛情・感謝・友情・尊敬から与えられるならば、個人の人生は幸福になる」。
しかし、人間は普遍的友情を持つことができない。そこで、自分の世話と見知らぬ人の世話を市場で交換する。例えば、「私はあなたが必要とする物をあなたにあげよう。その代わり私が必要とする物をあなたに求める」といった具合に。こうした説得に応じた交換は、自分への愛、すなわち自愛心にもとづくものであり、他者への愛情には基づいてはいない。しかし、生存を維持する方法としては有効である。そこでスミスは述べる、「交換とは、同感、説得性向、交換性向、そして自愛心という人間の性質に基づいて行われる互恵的行為である」。したがって市場は本来互恵の場であって、競争の場にはふさわしくないと。
第二に、市場においては無制限の利己心が放任されるべきだという考え方はスミスの思想からは決して出てこない。私たちは今一度スミスが利己心に基づいた自由な経済活動を容認したことの意味を正しくとらえなおす必要がある。自分の行為の基準として「一般諸規則」を考慮しなければならないという感覚を「義務の感覚」と呼ぶが、これをスミスは人類の行為を方向付ける最大重要性をもつ原理であるとする。義務の感覚が統制するものとしては、私たちが動物として本能的に持っている情念や欲望、それには自分の利益を第一に考えようとする「利己心」や「自愛心」も当然含まれる。私たちがどの程度まで本能的な欲望を解放してよいか、自分の利益を優先してよいかについては、常に一般的諸規則を顧慮しながら判断するのである。実際にスミスは「自然はわれわれを自愛心の妄想にすべて委ねてしまうことはなかった」と述べている。「利己心や自愛心は義務の感覚のもとに制御されなければならないし、通常は制御される」とスミスは考える。
第三に、「自然のもつ欺瞞」が経済を発展させ、社会を文明化する原動力になる、とする考え方をみてみよう。スミスは「経済を発展させるのは”弱い人”、あるいは私たちの中にある”弱さ”である」とする。「賢人」は最低水準を超える富の増加は幸福には影響しないと考える。
しかし最低水準の富を持っていても、心の弱い人はより多くの富を獲得して、より幸福な人生を送ろうと考える。そのような野心は幻想でしかないが、これはよい意味での自然のもつ欺瞞である。「孤立して生活している場合には持たなかった野心、すなわち虚栄心を持つことによって、人間は勤勉に働き、技能を磨き、収入を節約する。その結果土地が開墾され、海洋が開発され、都市が建設される。自然への働きかけによって、より多くの生活必需品が生産され、より大きな人口を養うことができるようになる。」
たとえそれが地主のための奢侈品の生産ではあっても、同時に生産される生活必需品は、その生産に参加したより多くの社会構成員に分配され、その結果、貧困にある人の数を減らすことができる。このようにして、地主の利己心と貧欲によって幸福が人々の間に平等に分配される。『道徳感情論』において、この仕組みは『見えざる手』と呼んだ唯一の箇所である。
第四に、相互の共感を基礎とした社会は国内ばかりでなく、国家間でも有効に機能するだろうか。スミスは、祖国への愛は自然で適切なものであると説く。しかし時として祖国への愛は倒錯したものとなり、国民的偏見を生み出す。そして諸国の自由な貿易こそ、このような交際を広める重要な手段となると述べる。
人間は、まずは自分自身の幸福を願い、次に自分の家族、そして友人や知り合いの幸福を願う。この序列をスミスは「愛着」と呼ぶ。愛着は「慣行的共感」によって深まる。つまり、日常生活で特定の人びとと繰り返し共感しあうことによって共感は深まり、頻度が低下するにしたがって希薄になる。まずは家族、次に友人や隣人、そして知り合いなどに愛着を持ち、その人の幸福を増進することが自分の幸福であり、時にそれは自分自身を犠牲にしてよいとまで考える。これが「祖国への愛」に深まるまで時間はかからない。彼らの繁栄と安全は、ある程度、国家の繁栄と安全に依存するからである。
しかし私たちの胸中の観察者は、祖国のために命を捨てる行為を「愛着の転倒」であると見抜く。自分自身とまわりの人々に対する愛着は自然なものであるが、それを超える祖国への愛は不自然で倒錯的なものになりがちである。国家の間においては中立的な観察者が存在しないため、私たちは近隣国民の繁栄と勢力拡大を、悪意に満ちた嫉妬と羨望をもって見るようになる。その結果、自国民に対しては守られる正義の感覚が他国民に対しては守られなくなる。「愛する人々に影響を与える国家に対する愛着を超えて、国がそれ自体で価値をもつと思われるようになるとき、人は自国が隣国よりも、あらゆる点で優れていることを望む」のである。これが国民的偏見である。
この環境を改善する方法として、相互の交際を深めることが挙げられる。それは第一で考察した市場の問題にかかわることでもあるが、諸国民間の自由な貿易こそ相互理解を深める手段ともなりうる。物の交換は、人と人との共感を前提にしなければ成り立たないからであり、また物の交換を繰り返すことによって人は取引相手をよりよく理解することができるからである。
以上四点にわたってスミスの道徳哲学を考察してきたが、グローバル化が進む中、リバタリアンをはじめとする市場原理主義者の言説が支配する環境にあって、人間の交際する場を「市場」としてとらえたスミスの視点は温かい。愛国心をめぐる論考もまた明快である。本書を通じ、従来スミスに抱いていたイメージ、すなわち国家は常に経済発展のために、規制を撤廃し、利己心に基づいた競争を促進することによって高い成長率を実現し、豊かで強い国を作るべきだとするイメージは完全に覆った。
※参考図書
堂目卓生(2008) 『アダム・スミス―『道徳感情論』と『国富論』の世界』 中央公論新社

2018年7月12日、20年前に上映された映画「ミュウツーの逆襲」がリメイク版として再び蘇り、映画館で公開上映された。ポケモン好きの私としては、勿論この機会を見逃す訳がなく、映画館まで足を運び見にいった訳だが、上映中、そのあまりの懐かしさに思わず涙が込み上げてきた。
私がこの映画を初めて見たのは確か6歳ぐらいの時だったと思う。そして、当時この映画を見た時「ミュウツーは強くてかっこいい!!」ぐらいの印象しか持たなかったが、今回改めて映画のリメイク版を見直した時、幼少期の頃に見た時とは違う感情が芽生え、そのあまりに奥深いテーマに感化されている自分がいる事に気づいた。そこで今回、「私はなぜミュウツーの逆襲を名作だと思うのか?」というタイトルのもと、この映画の魅力をご紹介していきたいと思う。

まず初めに、”ミュウツーの逆襲”のあらすじを簡単にご紹介しよう。
ミュウツーとは、幻のポケモン”ミュウ”の遺伝子をもとにして造られたポケモンである。”ミュウ”はあらゆる技を使いこなし、姿も自在に変えられることからポケモン界トップレベルの強さを誇る。そんな潜在能力に目をつけた研究者たちがいた。彼らは、ただ”最強のポケモンを生み出したい”という無邪気で無責任な思いから、ミュウの遺伝子をベースにある生命を生み出した。それが、”ミュウツー”である。
ミュウツーは生まれてすぐ、サカキ(反社会的組織ロケット団のボス)と行動を共にする。もともとミュウツーは、「なぜミュウのコピーである自分が生まれてきたのか…。」と、その意味をつかめないでいた。”最強”のポケモンとして、ただひたすらに戦っていれば、自分が何者であるのかを理解できると思ったのである。しかし、人間が自分の強さを好き勝手に利用することで、次第に自身の尊厳を傷つけられ、自分の存在意義についてより一層苦悩を極める事になる。そしてついに、ミュウツーはアジトを抜け出して、コピーである自分を勝手に生み出した人間と彼らと行動を共にするポケモンたちに、”復讐”を試みるのである。
具体的にミュウツーが行ったことは、あらゆるポケモンのクローンを生み出すことだった。自分の作り上げたクローンがオリジナルのポケモンを打ち負かすことで、”強さ”を持ってクローンの優位性を示すとともに、オリジナルの存在を否定しようとしたのである。オリジナルとクローンは自己の存在証明をかけて戦いを始め、最終的に泥沼の死闘に突入する。しかし、この惨状に心を痛め、止めにでた人間が現れた。主人公・サトシである。ミュウとミュウツーの激突に身を投じ、死を賭して終戦の願いを訴えたのである。クローンもオリジナルも、ポケモンも人間も関係なく、ノーサイドで生命のぶつかりあいを一身に引き受けたサトシ少年の行動を目の当たりにしたミュウツーは、”生きている実体”としてコピーにもオリジナルにも真偽はなく、”本物”を証明することの無意味さを悟るのである。その後、ミュウツーはコピーポケモンと共にその場を去り、どこかの孤島で彼らと静かに暮らすことになる。
以上が本作の概要であるが、ここからは、私の注目するポイントを挙げていきたい。
まず一つ目として、この映画はミュウツーが人間のエゴによって生まれたポケモンである事である。遺伝子操作による問題は、今でこそ世界中で大きく取り上げられている。最近で言えば、2018年の11月に中国でゲノム編集をした双子の赤ちゃんが誕生し大きな話題となった話が記憶に新しい。しかし、映画が上映された1998年当初、どれだけ多くの人たちが遺伝子操作による問題がここまで現実的なものになると予想していただろうか。1996年に世界初のクローン羊・ドリーちゃんが誕生し世間を騒がしていたとは言え、”意志”を持つ生物にまで科学技術が応用され、その存在をテーマに掲げたこの作品は、まさに時代を先駆けていたと言えるのではないだろうか。しかも、それが児童向けアニメの劇場版第一作目で扱われたのである。
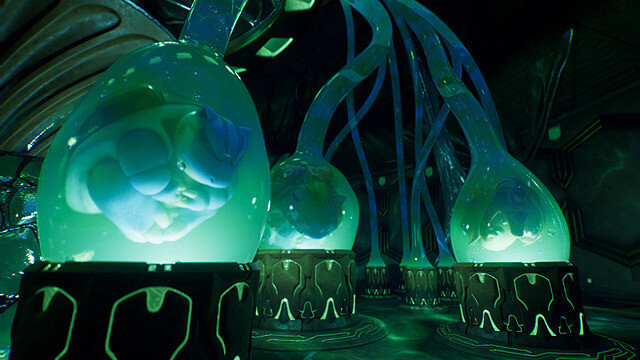
二つ目は、遺伝子ポケモンとして生まれたミュウツーの葛藤である。あらすじでも紹介したように、ミュウツーはミュウの遺伝子を組み換えて造られたポケモンである。その為、親もいなければ子供だった頃の記憶もない。そして、誰からの愛も受ける事なく育ってきた。では、ミュウツーのアイデンティティを保証してくれるものとは一体何なのだろうか。

私は誰だ。此処は何処だ。
誰が生めと頼んだ!誰が造ってくれと願った!
私は私を生んだ全てを恨む。
だからこれは、攻撃でもなく宣戦布告でもなく、
私を生みだしたお前たちへの・・・逆襲だ!
作中の中で、ミュウツーはクローンポケモンを作り出し、オリジナルのポケモンとバトルをさせる。そして、遺伝子操作により強化されたクローンポケモンがオリジナルのポケモンを圧倒していく。これは、ミュウツーが自身の強さにしか存在価値を見出せず、オリジナルの価値を否定する事で、自身のアイデンティティを保つ唯一の手段として現実に抗った結果なのだろう。
一方でオリジナルは、戦わずとも、もともとオンリーワンとして自分の対極に位置する傲慢な存在としてミュウツーには映っていた。ミュウツーの過剰な活動からは、ミュウツーの意識の奥にあるコピーポケモンとしての底知れぬ苦悩の大きさを見出すことができる。そして、だれよりも強く、苦しく、こう叫び、行動しなければ、ミュウツーは一つの独立した精神をもつ実体として存在できなかったのだ。

ミュウ、世界で一番珍しいと言われるポケモン。
確かに私はお前から作られた。
しかし強いのはこの私だ。本物はこの私だ!生き残るのは私だけだ!
最後に、本作品に散りばめられた台詞を振り返ることでエッセイのまとめとしたい。これまで見て来たように、ミュウツーの逆襲は、クローンとして生み出されたポケモン・ミュウツーの葛藤を描いた物語だ。その為、そんなミュウツーの葛藤から生み出されたストーリーは、人間の傲慢さ、生きる意味について数々の名言・問いとなって鑑賞している者の胸に深く突き刺さる。
・この世で別の命を作り出せるのは、神と人間だけだ
(ロケット団ボス・サカキ)
・本物は本物だ。技など使わずに体と体でぶつかれば、本物はコピーに負けない。
(幻のポケモン・ミュウ(ニャース翻訳))
・なんなの、この戦い。本物だってコピーだって、今は生きている。
(ポケモンセンター・ジョーイ)
・生き物は、同じ種類の生き物に、 同じ縄張りを渡そうとはしません。 相手を追い出すまで戦います、それが生き物です。
(ポケモンセンター・ジョーイ)
・生き物は、体が痛い時以外は涙を流さないって。悲しみで涙を流すのは、人間だけだって。
(アイツー(完全版のみ登場))
「みんな、どこへ行くの?」
「我々は生まれた、生きている、生き続ける、この世界のどこかで。」
(サトシ・ミュウツー)
以上、ミュウツーの逆襲の見所を紹介してきた。
他にも、クローンを扱った作品(ジュラシックパーク、私を離さないで、など)といった作品は数々発表されている。そうした作品に勝るとも劣らない内容をもって、幾重にも絡む生命の問題に切り込んだ作品が”ミュウツーの逆襲”である。ゆえに、私は本作品を愛するのである。もしこちらのエッセイを読んで少しでも興味が湧いた方には、是非一度この映画をお楽しみいただきたい。
※おまけ1
ポケモンについては、以前「私にとってポケモンとは?」というテーマでエッセイを書いています。もし興味のある方は、こちらも是非ご覧下さい!
※おまけ2
ミュウツーの逆襲名言紹介で、下記のフレーズを名言だと思う理由について友人がコメントを寄せてくれました。よろしければこちらもご覧下さい。
「みんな、どこへ行くの?」
「我々は生まれた、生きている、生き続ける、この世界のどこかで。」
(サトシ・ミュウツー)
コメント
あえて言えば、コピーだとか、逆襲だとか他人から押し付けられた事情を乗り越えて、自分の生と自分の責任で向き合う覚悟を感じる言葉だからかな。
誰しも望む望まずに関わらず生まれてきて、それぞれに逃れられない境遇があるわけだけど、それを嘆くでも否定するでもなく、命があるという事実をそのまま受け入れて(肯定するわけではない) 歩んでいこうとする言葉に、心の強さを感じた。
自分の不運、不遇、憎しみは生きる上でわかりやすい軸ではあるんだけど、その大元を取り除いたり、諦めてしまったら何も残らない。かといって、取り除かなければ一生もがくだけの人生で、どこまで生きていったって空っぽな自分が続くだけ。
ミュウツーも始めは自分vs他者いう構図を自分の中に明確に作り上げることで、生きている実感を強烈に燃え上がらせた。でも、出口もわからない真っ暗な暗闇の中を不安に煽られてただ闇雲に走り回るのと似た感覚だったかもしれない。闘い続けても復讐者以外の何者にもなれないこと、復讐対象という寄る方をなくした時に何も残らないことに実は気付いていて、1人では不安だった。それを否定したくて、同じ境遇にあるクローンをたくさん作って、強さこそ存在価値だということを、帰納的に証明しようとした。
でも、その過程でそれはやっぱり違ったという事実に気付いてしまった。自分以外が命と命をぶつかりあわせる光景を目の当たりにして、命の本質にオリジナルもコピーも無いことを聡明なミュウツーは悟った。でも、その事実を受け入れるということは、復讐の対象だった”人間”や”ミュウ”に存在理由を預けていた”楽な”現状と、強さを絶対の価値と自分に思い込ませて歩んできたこれまでの生き方を180度転換することを意味する。そして、今度は誰に依存するでもなく、自分自身で自分の存在理由を定義づけなくちゃいけない。これは他人から独立した試みだから、正解の基準は無いし、全て自分の責任で行わないといけない。だから、ミュウツーにとってすごく勇気のいることだと思う。
でも、そんな葛藤のあったはずのミュウツーだったのに、このセリフを言う時はすごく清々しかった。力みがなくて、自然体だった。あらゆる人間とポケモンに生まれてきた平等な事実があることを理解したことで、何より自分が救われたんだろうなって思った。“ミュウ”がいることが自分の存在価値、幸せを否定する理由にはならないんだってね。これからは自分が生み出してしまった”コピー”を含めて、真っ直ぐに世界と向き合っていくんだろうなって感じたし、オリジナルと幸せを共存して幸も不幸も共有することを肯定していくと思う。
なにかと言えば他人が気になって、自分の存在価値を疑ったり相対的に見てしまう世の中というか人間だからね、この言葉みたいに爽やかに、自律的に、力強く生きていきたいものだよね。
先日、近くの図書館を歩いていると、子連れの夫婦が図書館の入り口から出てきた。お父さんが子供に向かって何か話しかけていたので、そっと耳を傾けると、「こっちの道から帰るよ」と声をかけていた。ただ、その後である。お父さんについて行こうとする子供に、お母さんは「お父さんについて言っちゃダメ、こっちの道から帰るよ」と声をかけたのである。すると子供は、躊躇する事なくお母さんの後ろにドンドンとついて行き、お父さんも仕方なく向きを変え、心做しか、背中を小さく丸めながらお母さんの後ろについていった。
こうした場面は、よくある情景の一つかもしれない。私はこの光景を見て、「家庭内での立場はやっぱりお母さんの方が上なのかあ…」と、子に”無視”されてしまったお父さんに一人の男として同情を禁じ得なかったのだが、それと同時に、「なぜ家庭での立場は女性が”上”なのだろうか」とふと疑問に思った。
男女の社会的な平等さを示す指標として、”グローバル・ジェンダー・ギャップ指数”というものがある。このデータに基づくと、日本のジェンダー・ギャップ指数は2018年時点で世界149カ国中110位であり、決して男尊女卑が解消されたわけではない事がわかる。しかしその一方、家庭に絞ってみれば男性、すなわちお父さんの方があたかも”シリ”にしかれる現実があり、こうした家庭状況は文学、映像作品でもごく一般にお目にかかることができる。例えば、大ヒットしたドラマ・半沢直樹の悪役・大和田常務の妻や、アニメ・とある魔術の禁書目録の主人公・上条当麻のお母さんを見てみると、家庭内での影響力が男性よりも女性の方が上だとして描かれている。だが、その逆のパターンはあまり見た事がない。これは一体なぜなのだろうか…。
そこで今回、家庭でシリにしかれる男性に関心を寄せながら、生物学的な”オス”と”メス”を視点にこの謎を考えていきたいと思う。
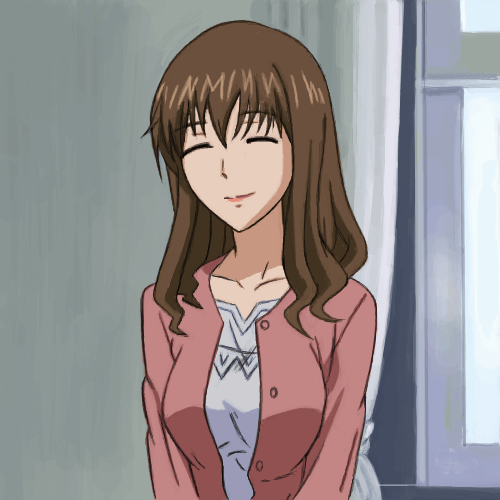
画像出典:ニコニコ大百科
生物は、もともと”単為生殖”という自身の基となる遺伝子をコピーして種を繁栄させてきた。これは、母が娘として自分の分身を生み出すのというものである。しかし、この単為生殖という方法には、生存上の大きな問題があった。それは、単為生殖が自分と全く同じコピーを生み出し続ける都合上、遺伝的多様性が低く、たった一つの環境変化や病によって絶滅する恐れが高いということである。
そこである生物は、自身の遺伝子を他個体の遺伝子と”混ぜる”ということを思いついた。”有性生殖”である。これにより、遺伝子の組み合わせがより多様になるだけでなく、外から別個体の有用な遺伝子を取り入れることが可能となった。その時、その遺伝子の運び手として誕生したのが”オス”である。当然、遺伝子の継ぎ手である”メス”は”オス”の持つ優れた遺伝子を確保しようとした。
その結果、メスはオスから有用な遺伝子を取り入れ、子に継がせることに成功する。しかし、メスのオスに対する要求は遺伝子にとどまらない。さらに、よりよい生存、育児環境を求めたメスは、オスは遺伝子の運び屋としての役割以外にもまだ使い道がある事に気付いた。”労働”である。人間で言えば、重い荷物を運ぶといった力仕事や獲物を狩るといったリスクの高い外仕事がこれにあたる。そして、メスは自らリスクを犯す必要なく子育てに専念する事が可能となった。遺伝子を残すという観点から見れば、この作戦は見事に功を奏したと言えるだろう。
しかし、この時メスにとって一つ予想だにせぬ事態が発生した。それは、各生物が自らの環境条件に適応した進化を遂げていく中で、メスの仕掛けた”ワナ”に背くオスが現れた事である。彼らは、メスの要求に従順に従うよう仕組んだ遺伝プログラムをも振り切り、外社会の権限を完全に自分たちの手によって支配してしまった。そして、そのオスを生み出したが種こそ、”ホモ・サピエンス(人間)”なのである。
話を戻そう。
現在の世界(特に日本)では、社会的観点から観れば、女性より男性の方が優遇されやすい場面が未だにたくさんある。しかし、”子孫を残す”(より究極的に言えば「遺伝子を継ぐ」)」という生物本来の役割に主眼を置いて考えるなら、間違いなくその世界での主人公は女性である。
こうした視点を取り入れ、冒頭で紹介した場面を振り返るなら、お父さんは、自らが女性から遺伝子の運び屋という”役目”を与えられた存在であることを本能的に察していたのではないだろうか。それは、子にとって、一から自らを育み、守ってくれるお母さんの優位は圧倒的であり、子供は無意識に格別の信頼を寄せているからかもしれない。お父さんにはそのことが分かるからこそ、後ろから母子の姿を見守り、付き従って行くしかないのである。私は、そんなお父さんの胸中を思うと、その家族からしばらく目が離せないのであった。
あとがき
今回のエッセイは、オリジナルではありますが、生物学者・福岡伸一先生の著書「できそこないの男たち」を一部参考にしました。もし興味のある方は是非こちらもご覧ください。
7月となり、今年も残すところあと半年となった。
歳を重ねた所為もあるのだろうか…最近は自身の年齢をやたら気にしてしまい、「人生の終活に向けての本質的な生の在り方とは何か」と考える事が多くなってきた。ここでいう ”本質的な生の在り方” とは、言い換えれば” 生きる目的とは何か” とか”人はなぜ生きるのか”という哲学的思考に近しいものである。私の同年代でこのような”死と生”に関わる問題について深刻に考える人は少ないかもしれない。しかし、あえて問いかけてみると、友人・知人たちは、”幸せな家庭を築く”、”生活を楽しく過ごすことが第一”という日常の幸せに生の在り方を見出そうとする考え方を提示してくれる。
だが、私の場合、この”本質的な生の在り方”という定義を考える時、どうしても ”日常の幸せ”に焦点を当てた考えではなく、”人は生きている間に何を残せるのか”という、自分の人生が社会に与える影響について考えずにはいられない。その理由については、もし私が生きている内に何かしらの痕跡や影響を残すことができれば、それが自身の分身として死後も社会を構成する一部となって生き続けてくれる、と考えているからだろう。では、誰もが社会に名を残せるような影響力ある人物になれるかというと、私も含め、多くの者が、スティーブ・ジョブズ、羽生善治、マイケル・ジャクソン、山中伸弥さんといった、誰もが知る人物になれる訳ではない。そうなると、社会に大きな功績を残せない者たちは、どのように社会における自分の生を意味づけることができるのだろうか。
そこで私は、ここで「ミーム」という考えを用いて、この問いを再考してみたいと思う。「ミーム」とは、生物学者リチャード・ドーキンスが提唱した造語であり「非遺伝的な複製子」を指す用語である。遺伝子(gene)が実態的に広がっていく複製子であるのに対し、ミームは非実態に広がる遺伝子の複製子、と思ってもらってもよいだろう。
例えば、哲学者ニーチェの本を読んで感動した大学生が、後にニーチェの思想を大学で教えるようになり、その講義を受け感化された生徒が、将来ニーチェの思想を研究するようになっていくとする。すると、ニーチェの思想が人から人へと受け継がれ、彼の思想が人々の記憶に留まり影響を与え続けることになる。このように、世代間を超えた遺伝情報のようなものがミームと呼ばれるものであり、先ほどの例で言えば、スティーブ・ジョブズ、羽生善治さんといった者たちがその格好のいい例となる。だが、ミームという考えをあまりに大きく捉えると、誰もが知る者たちの功績のみ語り継がれてしまい、そうでない者たちはミームを残せない事になる。そこで、ここではミームをもっと個人視点レベルまで落とし込んで再考してみたい。
これは、例えば、Aさんがおすすめする生物の本をBさんに貸し、Bさんはその本に深く感銘して生物学の道を目指し研究者になったとする。そして、長年の研究成果の末、Bさんは世紀に残るような大発見をしてノーベル賞を受賞することになるのだが、もしこの時、Aさんという人がいなければ、Bさんはノーベル賞を受賞するような偉大な成果を残すどころか、違う道を歩んでいった可能性があったかもしれない。つまり、ここで言いたいのは、Aさんが行った本を貸すという小さなミームの伝達が、バタフライ効果のように大きな連鎖反応を起こして、社会を大きく変えるような発見に結びつく可能性があるということである。その為、私たちが普段何気なく行っている些細な言動も個々人に特有の”ミーム”として、もしかしたら社会を大きく変えたり、人の運命を大きく左右するような複製子となっているかもしれない。そんな可能性に思いを馳せれば、自分自身の無力さに嘆く事なく、誰だって存在する意義を見つけ、存在した証を残すことができるのである。
私は普段、気に入った本を人に貸したり、ものをあげたりするのが好きなのだが、この行為は、私にとって”ミーム”を受け渡す行為にほかならず、いずれ社会を変えるような変革に結びつくかもしれないと思う期待なのである。勿論、こうした行動に対してどう解釈し行動するかは受け取った本人次第であり、必ず誰かの社会的功績に結びつくとは限らない。それでも、生きている者同士が積極的にミームのやりとりができたなら、人は刺激的な環境で生き生きと夢や好奇心を抱きながら、毎日を過ごすことができるのではないだろうか。









