ESSAY
シリにしかれる男たち
先日、近くの図書館を歩いていると、子連れの夫婦が図書館の入り口から出てきた。お父さんが子供に向かって何か話しかけていたので、そっと耳を傾けると、「こっちの道から帰るよ」と声をかけていた。ただ、その後である。お父さんについて行こうとする子供に、お母さんは「お父さんについて言っちゃダメ、こっちの道から帰るよ」と声をかけたのである。すると子供は、躊躇する事なくお母さんの後ろにドンドンとついて行き、お父さんも仕方なく向きを変え、心做しか、背中を小さく丸めながらお母さんの後ろについていった。
こうした場面は、よくある情景の一つかもしれない。私はこの光景を見て、「家庭内での立場はやっぱりお母さんの方が上なのかあ…」と、子に”無視”されてしまったお父さんに一人の男として同情を禁じ得なかったのだが、それと同時に、「なぜ家庭での立場は女性が”上”なのだろうか」とふと疑問に思った。
男女の社会的な平等さを示す指標として、”グローバル・ジェンダー・ギャップ指数”というものがある。このデータに基づくと、日本のジェンダー・ギャップ指数は2018年時点で世界149カ国中110位であり、決して男尊女卑が解消されたわけではない事がわかる。しかしその一方、家庭に絞ってみれば男性、すなわちお父さんの方があたかも”シリ”にしかれる現実があり、こうした家庭状況は文学、映像作品でもごく一般にお目にかかることができる。例えば、大ヒットしたドラマ・半沢直樹の悪役・大和田常務の妻や、アニメ・とある魔術の禁書目録の主人公・上条当麻のお母さんを見てみると、家庭内での影響力が男性よりも女性の方が上だとして描かれている。だが、その逆のパターンはあまり見た事がない。これは一体なぜなのだろうか…。
そこで今回、家庭でシリにしかれる男性に関心を寄せながら、生物学的な”オス”と”メス”を視点にこの謎を考えていきたいと思う。
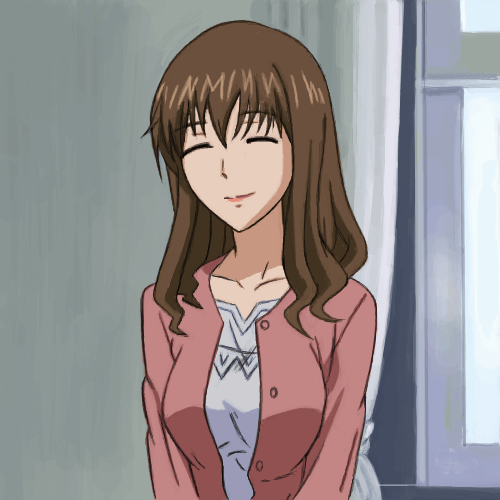
画像出典:ニコニコ大百科
生物は、もともと”単為生殖”という自身の基となる遺伝子をコピーして種を繁栄させてきた。これは、母が娘として自分の分身を生み出すのというものである。しかし、この単為生殖という方法には、生存上の大きな問題があった。それは、単為生殖が自分と全く同じコピーを生み出し続ける都合上、遺伝的多様性が低く、たった一つの環境変化や病によって絶滅する恐れが高いということである。
そこである生物は、自身の遺伝子を他個体の遺伝子と”混ぜる”ということを思いついた。”有性生殖”である。これにより、遺伝子の組み合わせがより多様になるだけでなく、外から別個体の有用な遺伝子を取り入れることが可能となった。その時、その遺伝子の運び手として誕生したのが”オス”である。当然、遺伝子の継ぎ手である”メス”は”オス”の持つ優れた遺伝子を確保しようとした。
その結果、メスはオスから有用な遺伝子を取り入れ、子に継がせることに成功する。しかし、メスのオスに対する要求は遺伝子にとどまらない。さらに、よりよい生存、育児環境を求めたメスは、オスは遺伝子の運び屋としての役割以外にもまだ使い道がある事に気付いた。”労働”である。人間で言えば、重い荷物を運ぶといった力仕事や獲物を狩るといったリスクの高い外仕事がこれにあたる。そして、メスは自らリスクを犯す必要なく子育てに専念する事が可能となった。遺伝子を残すという観点から見れば、この作戦は見事に功を奏したと言えるだろう。
しかし、この時メスにとって一つ予想だにせぬ事態が発生した。それは、各生物が自らの環境条件に適応した進化を遂げていく中で、メスの仕掛けた”ワナ”に背くオスが現れた事である。彼らは、メスの要求に従順に従うよう仕組んだ遺伝プログラムをも振り切り、外社会の権限を完全に自分たちの手によって支配してしまった。そして、そのオスを生み出したが種こそ、”ホモ・サピエンス(人間)”なのである。
話を戻そう。
現在の世界(特に日本)では、社会的観点から観れば、女性より男性の方が優遇されやすい場面が未だにたくさんある。しかし、”子孫を残す”(より究極的に言えば「遺伝子を継ぐ」)」という生物本来の役割に主眼を置いて考えるなら、間違いなくその世界での主人公は女性である。
こうした視点を取り入れ、冒頭で紹介した場面を振り返るなら、お父さんは、自らが女性から遺伝子の運び屋という”役目”を与えられた存在であることを本能的に察していたのではないだろうか。それは、子にとって、一から自らを育み、守ってくれるお母さんの優位は圧倒的であり、子供は無意識に格別の信頼を寄せているからかもしれない。お父さんにはそのことが分かるからこそ、後ろから母子の姿を見守り、付き従って行くしかないのである。私は、そんなお父さんの胸中を思うと、その家族からしばらく目が離せないのであった。
あとがき
今回のエッセイは、オリジナルではありますが、生物学者・福岡伸一先生の著書「できそこないの男たち」を一部参考にしました。もし興味のある方は是非こちらもご覧ください。
