-
2022.08.07
はちみつ Handbook(一般社団法人 全国はちみつ公正取引協議会青年部 構成)
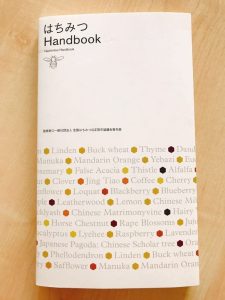
蜂蜜の基礎知識や様々な花の蜜の特徴などをまとめた本です。 40種類の単花みつのプロフィールなどがわかりやすく掲載されている、 ハンディーサイズの本です。 ミツバチが蜜を取る40種類の花の絵を、描きました。 なぜ、ミツバチは蜜を集めるのか。花の蜜と蜂蜜の違い等、 私たちが知っている知識よりもさらに詳しく知ることが出来ます。 (Amazon内容紹介) 最近、仕事の関係で蜂蜜を取り扱うようになり本書を手に取ってみたがなかなかに面白い。そこで、ここでは本書でまとめられていた蜂蜜の知識を一部紹介してみたいと思う。 1はちみつが出来上がるまでの過程働きバチは花から吸い取った蜜をお腹の中にある「蜜胃」と呼ば…
-
2021.10.23
はたらく細胞
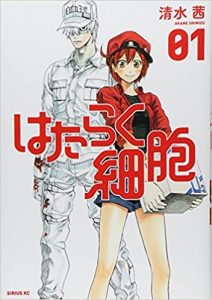
人間1人あたりの細胞の数、およそ60兆個! そこには細胞の数だけ仕事(ドラマ)がある! ウイルスや細菌が体内に侵入した時、アレルギー反応が起こった時、ケガをした時などなど、白血球と赤血球を中心とした体内細胞の人知れぬ活躍を描いた「細胞擬人化漫画」の話題作、ついに登場!! はたらく細胞
-
2021.08.01
ドラゴン桜
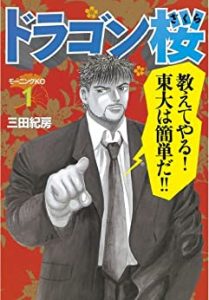
「教えてやる!東大は簡単だ!!」常識破り、処世術。弁護士・桜木による落ちこぼれ高校の再建計画、その内容は東大合格者100人!! 日本のルールは東大を出たやつが作っている。だから……東大に入れ!! もっとも効率的な学習法を教えよう!! ドラゴン桜 ドラゴン桜2
-
2020.09.19
成功する子 失敗する子 – 何が「その後の人生」を決めるのか –

人生における「成功」とは何か?好奇心に満ち、どんな困難にも負けず、なによりも「幸せ」をつかむために、子供たちはどんな力を身につければいいのだろう?神経科学、経済学、心理学…最新科学から導き出された一つの「答え」とは―?アメリカ最新教育理論。(著者:ポール・タフ, 訳:高山真由美) 本書は、人生における”幸せ”を掴む為、幼少期の子供教育に焦点を当てた話を展開している。話の中では、読み書きや学力のようなIQで測れる認知能力に対し、やり抜く力・好奇心・自制心のような数字で測る事のできない非認知能力にスポットを当てられているが、そこで紹介されている数々の事例がとても興味深い。 例えば、ストレスに…
-
2020.07.30
ペスト
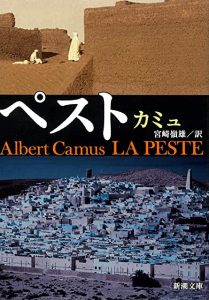
アルジェリアのオラン市で、ある朝、医師のリウーは鼠の死体をいくつか発見する。ついで原因不明の熱病者が続出、ペストの発生である。外部と遮断された孤立状態のなかで、必死に「悪」と闘う市民たちの姿を年代記風に淡々と描くことで、人間性を蝕む「不条理」と直面した時に示される人間の諸相や、過ぎ去ったばかりの対ナチス闘争での体験を寓意的に描き込み圧倒的共感を呼んだ長編。(著者:アルベール・カミュ, 訳:宮崎嶺雄) 「新型コロナウイルス」の世界的流行が始まってから、アルベール・カミュの著書『ペスト』に注目が集まっている。この物語は、アルジェリアのオランという町で未知のウイルス「ペスト」が発生し、その時の様…
-
2020.05.31
四色問題

四色あればどんな地図でも塗り分けられるか?一見簡単そうだが、どうにも証明できない難問として人々の頭を悩ませ続けた「四色問題」。ルイス・キャロルをはじめ幾多の人物が挑戦しながら失敗。一世紀半後、ふたりの数学者がコンピュータを駆使して解決するが、「これは数学じゃない」と拒絶反応も。天才たちの苦闘の歴史を通じ、世紀の難問が解かれるまでを描く興奮の数学ドラマ。(著者:ロビン・ウィルソン 訳:茂木健一郎) 四色問題とは、1850年初めに提唱された問題であるが、その問いは以下のようなものである。 四色あれば、どんな地図でも隣り合う国々が違う色になるように塗り分けることができるか この問題を理解するだ…
-
2020.04.18
斜陽

敗戦後、元華族の母と離婚した“私”は財産を失い、伊豆の別荘へ行った。最後の貴婦人である母と、復員してきた麻薬中毒の弟・直治、無頼の作家上原、そして新しい恋に生きようとする29歳の私は、没落の途を、滅びるものなら、華麗に滅びたいと進んでいく。(著者:太宰治) 「斜陽」は、没落していく貴族の生活を描いた作品だが、その様相は暗さの中に耽美的な美しさを感じさせるストーリーである。その象徴的な場面が、主人公・かず子を通して描かれるお母様の姿だろう。まず、作品の冒頭では、お母様がスウプを飲む姿を描いているが、その姿が何とも上品で美しく、それ以降も、放蕩息子・直治を思いやる姿、娘・かず子を慈しむ描写は印象的…
-
2020.04.09
アルケミスト
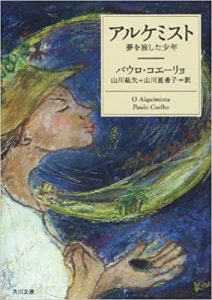
半飼いの少年サンチャゴは、その夜もまた同じ夢を見た。一週間前にも見た、ピラミッドに宝物が隠されているという夢。少年は夢を信じ、飼っていた羊たちを売り、ひとりエジプトに向かって旅にでる。アンダルシアの平原を出て、砂漠を越え、不思議な老人や錬金術師の導きと、さまざまな出会いと別れをとおし、少年は人生の知恵を学んでいく。(著者:パウロ・コエーリョ) 全世界で81カ国語に翻訳され、8500万部の売り上げを誇っているアルケミスト。その内容は、宝物の夢を見た少年が、その夢を追いかけ旅に出るという物語だ。話の中では「前兆」「心の声」「大いなる魂」といったスピリチュアルめいた言葉が数多く登場するが、それは、…
-
2020.04.04
正義の教室
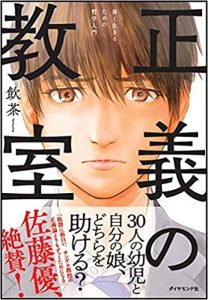
ソクラテス、プラトン、ベンサム、キルケゴール、ニーチェ、ロールズ、フーコーetc。人類誕生から続く「正義」を巡る論争の決着とは?私立高校の生徒会を舞台に、異なる「正義」を持つ3人の女子高生のかけ合いから、「正義」の正体があぶり出される。(著者:飲茶) 本書は、生徒会長である今中正義を中心に、功利主義者である最上千幸、自由主義者であるリバティ・ミユウ・フリーダム、直観主義者の徳川倫理、そして倫理の授業を行う風祭先生を巻き込んで「正義とは何か?」について考えていく。哲学自体をテーマにした小説は珍しいが、話の中でも登場人物の過去に触れた様々な伏線が散りばめられているので、読んでいる者を飽きさせな…
-
2020.03.28
史上最強の哲学入門 東洋の哲人たち
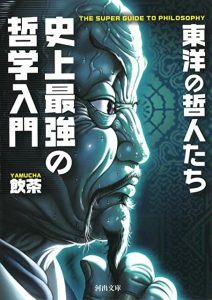
最高の真理を求める男たちの闘い第二ラウンド!古代インド哲学から釈迦、孔子、孟子、老子、荘子、そして日本の禅まで東洋の“知”がここに集結。真理(結論)は体験によってのみ得られる!(著者:飲茶) 哲学といえば、生きるとは何か、死とは何か、存在とは何か、といった抽象的な問いを考察していく学問だが、哲学者の考えを知るとなると、超人思想・脱構築・構造主義といった専門用語が立ち並び、理解するのが難しい。だが、本書では「史上最強の哲学入門」とタイトルにあるように、各哲学者の思想や造語を大変分かりやすく紹介している。そして本作は、東洋哲学の偉人に焦点を当てた構成となっているが、そもそも東洋哲学はどのような…